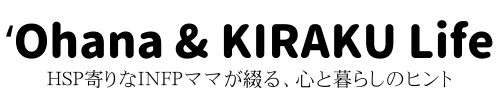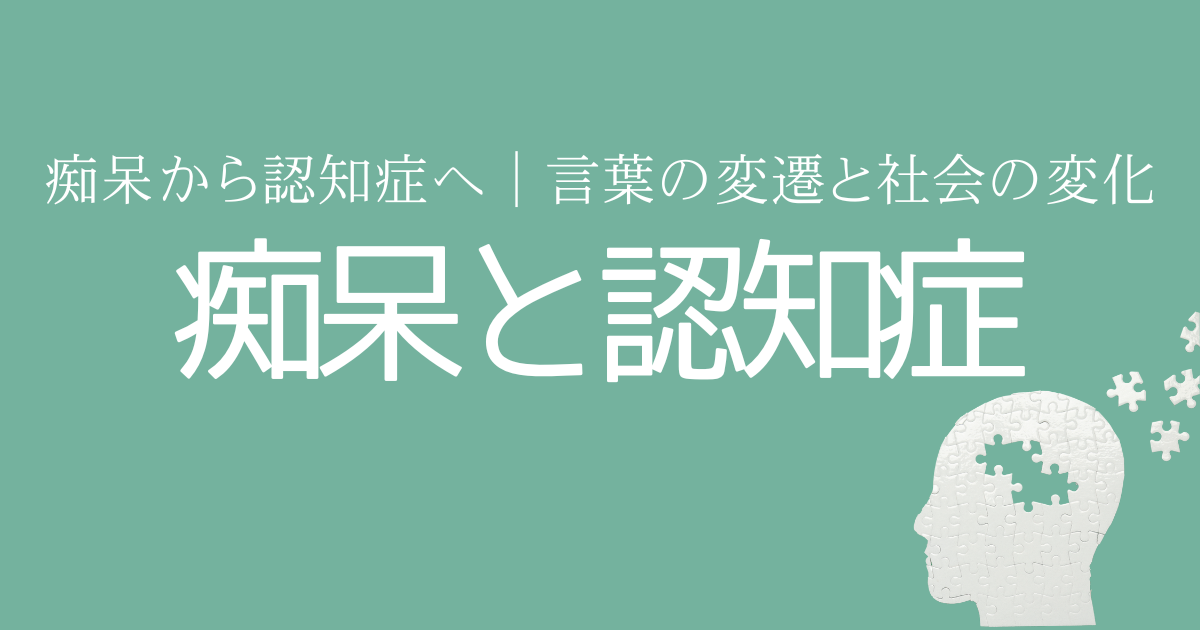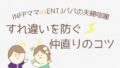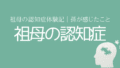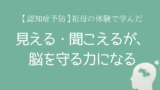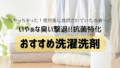私の祖母は認知症を患っています。
あるとき、年配の方が「認知症」を「痴呆」と表現していたのを耳にして、呼び方に違いがあることに気づきました。🤔
私にとっては「認知症」のほうが馴染みがあり、今ではその言葉のほうが適切だと感じています。
では、いつから「痴呆」ではなく「認知症」と呼ばれるようになったのでしょうか?
↔️「痴呆」と「認知症」の言葉の変遷
「痴呆」と「認知症」は、どちらも認知機能の低下を指す言葉ですが、歴史的な背景や意味が異なります。以下にその主な変遷をまとめます。
1. 痴呆(ちほう)
- 昔の表現:「痴呆」は、昭和時代から日本で使われてきた言葉で、認知機能の低下とそれによる日常生活の支障を指していました。
- 問題点:この言葉には「愚か」や「知能が低い」といった侮蔑的なニュアンスが含まれ、患者や家族にとって不快に感じることがありました。
2. 認知症(にんちしょう)
- 1980年代の変化:1980年代に入ると、医学的な進展とともに「痴呆」に代わって「認知症」が広く使われるようになりました。
- 背景:より中立的な意味を持ち、偏見を減らすための言葉として定着していきました。
1980年代は、日本でも世界でも大きな変化の時代。
日本はバブル経済の前兆を迎え、家庭にはパソコンやテレビゲームが普及しました。社会全体が急速に変化するなかで、認知症に対する認識も大きく変わっていったのです。
3. 認知症の多様化
- 現代の認識:「認知症」という言葉は、単一の病気を指すものではなく、記憶や思考の低下に加え、感情や行動の変化を伴う広範な状態を表すようになっています。
- 研究の進展:早期診断や予防、治療法の研究が進み、支援体制も充実しています。
🏙️言葉の変遷と社会的影響
「痴呆」から「認知症」への名称変更には、医学的理解と社会的な配慮が反映されています。
新しい言葉が使われるようになったことで、患者やその家族への理解が深まり、偏見や差別を減らす社会的な取り組みも進んできました。
現在では、さらに配慮のある言い方が求められることもあり、
「認知症型疾患」や「認知機能障害」といった表現も使われています。
これは、病気に対する偏見を避け、個人の尊厳を守るための一環です。
🎭まとめ
| 時代 | 呼び方 | 補足 |
|---|---|---|
| 昔 | 痴呆(ちほう) | 侮蔑的なニュアンスがあり変更 |
| 現在 | 認知症(にんちしょう) | 医学的・社会的に定着 |
私(INFP/仲介者)の個人的な感覚では、やはり「痴呆」よりも「認知症」と呼ぶほうがしっくりきます。
祖母が認知症を患っていることもあり、「痴呆」という言葉にはどうしても差別的な印象を感じてしまう部分があることは否めません。
気にしない方もいらっしゃると思いますが、気になる方も当然いると思うので、言葉の変遷の背景からも私は「認知症」という言葉を選びたいと思います。💭
■このブログについて | ʻOhana & KIRAKU Life